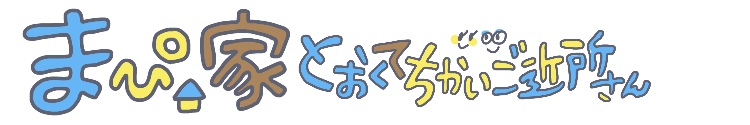3.毒抜きの方法
marcy
栽培種ができるためには、
まずは野生種を利用しないと
いけないですよね。
tomo
はい、そうですね。
marcy
でも、野生種のじゃがいもは、
めっちゃソラニン濃度が高い。
つまり、これを利用するためには、
毒抜きの方法を発見しないといけない。
tomo
はい、はい。
marcy
ただし、やっき見た通り、
加熱では分解されない。
ではどうやって、
原住民たちは毒抜きをしたのかを
見ていきます。
tomo
これ、めっちゃ気になりますね。
marcy
僕は知ってしまっているのでアレですが、
どうやったと思いますか(笑)
tomo
そうですね…加熱は試しているとして、
他の方法…ん~
少し水に溶ける要素があったので…
marcy
おぉ!
tomo
水に浸けるとか、
その水にアルカロイドを
吸着してくれる野草みたいなのを
入れるとか…。
marcy
なるほどです(笑)
ではまず現地のこと、
中央アンデス高地の
気象条件から把握しておきます。
tomo
はい。
marcy
中央アンデス高地は、
10月~3月までが雨季。
雨が大量に降る。
そして4月~9月が乾期。
乾期は、湿度が低い。
かつ、一日の気温変化が
非常に激しい時期です。
tomo
なるほど。
marcy
日中は熱いけど、
夜は氷点下(-5~6℃)になるのが
この地域の環境です。
tomo
はいはいはい。
激しい環境ですね、これは。
marcy
そうそう。言い換えると、
この環境があったから、
いもという植物が存在した。
乾期を乗り越えるために、
養分を蓄えたと言ってましたよね。
同時に、毒抜きもこの環境を
利用しています。
tomo
えぇ!
marcy
さぁ、どんな方法が
考えられるでしょうか(笑)
pino
ん~…
茹でて干して、茹でて干してを
繰り返す。
marcy
おぉ!すごいいいとこいってる!
茹でてはないんだけど、
仕組みは合ってる。
pino
水に浸けるの?
marcy
浸けはしないんだけど、
じゃあ見ていこう。
pino
うん。
marcy
まず乾期に、
外にじゃがいもを並べて広げ
放置します。
pino
へぇ~。
marcy
乾期は、夜に気温がぐっと下がるので、
夜にじゃがいもが凍ります。
tomo
はい。
marcy
次の日中、
そのまま置いておいたら、溶けます。
tomo
ほうほう。
marcy
これを繰り返すと、
組織の中の水分が、
凍って溶けてを繰り返し、
細胞が壊れ、
水分がしみ出る状態になります。
この、ブヨブヨになった状態のものを
集めて足で踏むと、
脱水ができるようになります。
pino
ふ~ん。
marcy
そうすると水分がジューと出てくる。
今度はこれを数日間放置すると、
湿度が低く気温が高いおかげで
乾かすことができる。
tomo
なるほど~。
marcy
ソラニンは、細胞の中の
液胞に存在することが多いので、
細胞を壊した状態で水分を絞れば、
ソラニンも出ていく。
pino
へぇ~!
marcy
こんな方法を発見して、
野生種のじゃがいもを
利用していたようです。
tomo
なるほど!
marcy
ちなみに、こうやって毒抜きして
乾燥したものを「チューニョ」と呼びます。
tomo
チューニョ。
marcy
現在も作られているそうで、
大きさはゴルフボールの1/2~1/3くらい。
状態がよければ、
数年は保存できるみたいです。
tomo
めっちゃ保ちますね。
marcy
うんうん。
これ、おもしろいのが、
日本にもチューニョと似た方法で作る
保存食があるんですよ。
tomo
まじですか。
marcy
山梨県に「凍み芋」と呼ばれる
伝統食があって。
これは掘ったじゃがいもを放置して、
夜に凍結、昼に解凍を繰り返して
自然乾燥させる。
山梨県鳴沢地域の伝統食。
富士山がある辺りですね。
tomo
へぇ~!
marcy
北海道にも「しばれ芋」という
似た保存食があります。
もちろん、日本にじゃがいもが
やってきたときは、
すでに野生種ではないです。
でもこの3つが作られているのは、
どれも寒い地域ですよね。
寒い地域で条件がそろい
じゃがいもを利用したいと思うと、
外の情報を知らなくても
みんな同じ方法に辿り着く、
というおもしろさがあります。
tomo
ほんとだ(笑)
marcy
なぜ、寒い地域で
同じ方法になるのかというと、
寒いということは、
穀物が育ちにくい。
すると、食料はいも類などに
依存しがちになる。
tomo
うんうん。
marcy
でも、生のじゃがいもなどは、
長期間保存できないので、
乾燥品にする必要がある。
そのときどうやるかというと、
凍らして解かして乾かすという
結論に辿り着く。
これがおもしろいなぁって。
tomo
すごいですね(笑)
marcy
外部環境がそろうと、
似た行動になるんだなぁと。
tomo
うんうん。
marcy
こんな感じで、アンデス現地の人々は
毒抜きの方法を発見して、
野生種を利用して、
何千年もかけて栽培種をつくった。
そして現在の僕たちが食べているのは、
たった1種類の栽培種。
tomo
うわぁ、そうだったんだ。
marcy
僕たちは今日の前半部分で、
じゃがいもには毒があるから気をつけよう、
という話をしてましたけど、
野生種を利用していた当時の人からしたら、
「そんなのほとんど毒入ってないやん!」
くらいのノリです(笑)
pino
(笑)
tomo
なるほど(笑)
marcy
もしこの方法が発見されてなかったら、
野生種を利用することができず、
栽培種にはつながらなかった。
tomo
そうか、そうか。
marcy
原産地で栽培種ができなかったら、
世界中に広まることもなかった。
なぜかというと、
ヨーロッパにはそもそもイモがないし、
日本にもじゃがいもはなかったので。
tomo
そうですよね。
marcy
だから、アンデスの原住民、
マジサンキューということです。
pino
(笑)
tomo
ありがとう(笑)
だって、何千年もちょっとずつ
やっていったわけですもんね。
marcy
そうそう。
ちょっと大きいのがあるから
コイツを増やそうとか、
そんな繰り返しですよね。
なんでそんな努力をしたのかも
さっき言った通り、
アンデスが高地すぎて
普通の作物が育たないからで。
小麦や稲は育たないし、
トウモロコシは食べているんですが、
育つ標高にも限界がある。
じゃがいもはそれよりも
高い地域で育つので、
これを利用しないといけない。
だから、これだけ毒があっても
なんとか利用しようと続けてきた。
もし、他に都合のいい作物があれば、
この努力はしていなかっただろうと
思います。
tomo
なるほど。
必要にせまられて、
知恵を絞った感じですね。
すごいな、ふつうはこれだけ毒があれば
食べるのやめそうですけど、
他のものに比べれば
可能性があったのでしょうね。
marcy
そうでしょうね。
今、この野生種があったとしても、
僕らは利用する努力をしないでしょうから。
でも、これしかないとなったら、
なんとか工夫すると。
tomo
あとは、おいしかったのかも
しれないですよね。
marcy
たしかに。
でんぷんを蓄えているから、
本能的にエネルギー源になることは
感じられたのかもしれないですね。
糖質だから。
tomo
なるほど。
食べられる、けど、
お腹痛くなるしなんとかしよう…って。
marcy
そうですよね、
ぜったい途中で何人も
中毒起こってますよね。
tomo
何人も起こってますね。
marcy
でもそれを乗り越えて発見するのが、
やっぱりすごいです。
tomo
すごいなぁ。
marcy
以上、もっとも身近な毒である
じゃがいものソラニンは、
こんな感じで始まったよというお話でした。
tomo
おもしろいですねぇ~
ありがとうございました。
*参考文献を基にしておりますが、厳密な考証は行っておりません。あくまで「趣味のおしゃべり」として、楽しんでいただけると幸いです。
参考文献
ジャガイモのきた道/山本紀夫/岩波新書/2008
ジャガイモの世界史/伊藤章冶/中公新書/2008
ジャガイモの歴史/アンドルー・F・スミス/原書房/2014
へんな毒 すごい毒/田中真知/ちくま文庫/2016
世界史を大きく動かした植物/稲垣栄洋/PHP/2018
海が運んだジャガイモの歴史/田口一夫/梓書房/2016
食中毒統計資料令和4~元年/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
食品中の天然毒素「ソラニン」や「チャコニン」に関する情報/農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/solanine/
有毒植物による食中毒に注意しましょう/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html