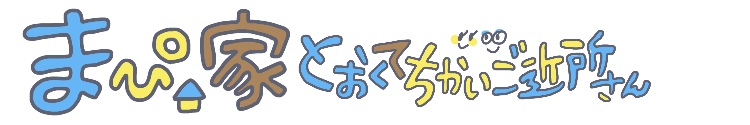2.どうやって栽培化した?
marcy
では、そのじゃがいもを
原住民のヒトたちが
どうやって栽培化していったのか。
これは明確な資料が
残っているわけではなく、
文字を扱う文化ではなかったので、
予想するしかないんですが…
pino
うんうん。
marcy
そもそも野生のじゃがいもは、
僕たちが知っているじゃがいもの
数倍のソラニンを持っています。
tomo
へぇー。
marcy
それと、
小指の先くらいの大きさと言った通り、
じゃがいもとは思えないくらい小さい。
もとはそんな存在のじゃがいもを
利用しようと思うと、
まずは「毒抜きの方法」を
発見しないといけない。
tomo
なるほど。
marcy
毒抜きの方法を発見する、
利用する、
また植える、
植えたら増える。
植物の品種改良は自然界でも起こるので、
植えてきたものの中で
突然変異的に大きいものや
毒素が少ないものを選び、
また繰り返し栽培する。
こんなことを、
ずーっとやってきたと考えられます。
pino
うんうん。
marcy
これを繰り返すと、
やがて比較的実が大きくて、
毒素が少ないものができてくる。
この「栽培化」がされたのは
紀元前5000年頃とされているので、
7000年くらい前にはできていた
と考えられます。
tomo
けっこう前ですね~。
marcy
そうですね、何千年も
ずーとそういうことをやって、
やっと栽培種ができた。
tomo
へぇー。
pino
ふ~ん。
marcy
だから、
いま僕らの「新しい品種ができたね」
という感覚と比べると、
とんでもない長い年月をかけて
やっと野生種が栽培種に変化したのが、
じゃがいも栽培の歴史のスタートです。
tomo
なるほど。
marcy
ちなみに、そうやって
「栽培種」になったじゃがいもは、
7種類あります。
pino
へぇ~。
marcy
そして、いま世界中で
じゃがいもが食べられていますが、
これを「栽培種」という視点でみると、
使われているのは
「ソラヌム・トゥベローサム」という
1種類だけです。
tomo
そうなんですね!
marcy
つまり、この1種類の栽培種から
いろいろな品種ができている、
という理解です。
男爵やメークイン、アンデスレッドも全部
大きな分類でみれば、同じ仲間。
pino
うんうん。
marcy
残り6種の栽培は
アンデス周辺に限られるので、
基本的に世界中のじゃがいもは
すべて同じヤツです(笑)
tomo
なるほど~!
marcy
品種でみるか、
植物的な種でみるか、
の違いですね。
tomo
残りの6種は、
まだ食べられていないってことですか。
marcy
現地では食べられているようですが、
世界中で栽培するときに
それらを選ぶメリットは少ない、
だから広がらないってことですね。
tomo
あぁ、そういうことですね。
marcy
なので、
もし「このじゃがいもは何でしょう」と
質問されたときは、とりあえず
「トゥベローサム」って答えたら、
ぜんぶ正解です。
pino
(笑)
tomo
視野が広い(笑)
marcy
こんな感じで、じゃがいもは、
まずは野生種を発見して利用し、
だんだん栽培種に変化させていく
ということを、やってきました。
tomo
ん~なるほど。
やっぱり、そういう
何千年という歴史があるんですねぇ。
*参考文献を基にしておりますが、厳密な考証は行っておりません。あくまで「趣味のおしゃべり」として、楽しんでいただけると幸いです。
参考文献
ジャガイモのきた道/山本紀夫/岩波新書/2008
ジャガイモの世界史/伊藤章冶/中公新書/2008
ジャガイモの歴史/アンドルー・F・スミス/原書房/2014
へんな毒 すごい毒/田中真知/ちくま文庫/2016
世界史を大きく動かした植物/稲垣栄洋/PHP/2018
海が運んだジャガイモの歴史/田口一夫/梓書房/2016
食中毒統計資料令和4~元年/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
食品中の天然毒素「ソラニン」や「チャコニン」に関する情報/農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/solanine/
有毒植物による食中毒に注意しましょう/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html