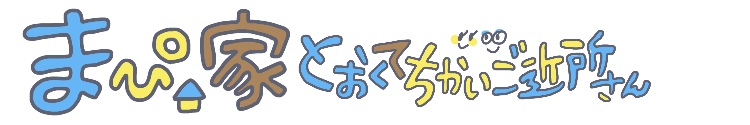第5話 野生種と毒抜き

メンバー


1.野生種という視点で見る
marcy
これまで、
じゃがいもには毒があるよ
それに注意しよう
という話をしてきました。
tomo
はい。
marcy
この話のベースにあるのって、
すべて「栽培種」なんです。
tomo
ほう。
marcy
つまり、
今まで頭でイメージしていたじゃがいもは、
ヒトが栽培種として育てて、広めて、
収穫して、食べているじゃがいも。
tomo
なるほど。
marcy
でも、栽培種があるということは、
その手前に「野生種」もあるんですよね。
tomo
うんうん。
marcy
ふだんの僕らが野生種に
触れる機会はないので
馴染みはないんですが、
一回、この野生種時代の
じゃがいもについて見てみよう
というのが、ラストのテーマです。
tomo
おぉぉ、めっちゃ興味あります。
pino
(笑)
marcy
よかった(笑)
ではまず、じゃがいもの
原産地はどこでしょう??
tomo
えっと、アンデス、南米。
marcy
そうです。じゃがいもの原産地、
野生種が生まれたのは、
南アメリカ大陸のアンデス高地と
考えられています。
tomo
はい。
marcy
そして、
現在も一応野生種はありますが、
いもの部分は、だいたい
小指の先くらいの大きさです。
tomo
えぇー、そうなんですか(笑)
marcy
また、基本的に毒が多いので、
現地のヒトは食べないそうで。
ヒトが食べないいもなので、
「キツネのジャガイモ」と
呼ばれているみたいです。
pino
へぇ(笑)
tomo
キツネなんですね(笑)
marcy
キツネは食べるんですかね(笑)
いったん、アンデス地域を復習しておくと、
南アメリカ大陸を太平洋沿岸に沿って走る
地球上で最長の山脈地域です。
南北に8,000km、
標高4000~6000m。
富士山より高い場所が
ずっと続いているような地域ですね。
tomo
はい。
marcy
ここは、北部・中部・南部に
分かれています。
北部は、赤道付近で熱い地域。
ベネズエラやコロンビア辺り。
中部はペルーやボリビア。
そして南部が、
チリやアルゼンチンの辺りです。
標高はかなり高いんですが、
全体的に熱帯で気候が安定しているので、
高地でも人が住める環境である
とされています。
pino
ふ~ん。
marcy
じゃがいもはこの中でも、
主に中部アンデスに存在します。
そしてこの地域は、
もともとイモを付ける植物が多い。
なぜかというと、
雨季と長い乾季を繰り返す気候なので、
植物たちは乾期の間を
生き延びないといけない。
そのために、地下茎や根に養分を貯蔵する
という対策をとるためです。
tomo
なるほど~。
marcy
このような環境で、
じゃがいもは生まれました。
tomo
野生の、じゃがいも。
marcy
そうです、そうです。
*参考文献を基にしておりますが、厳密な考証は行っておりません。あくまで「趣味のおしゃべり」として、楽しんでいただけると幸いです。
参考文献
ジャガイモのきた道/山本紀夫/岩波新書/2008
ジャガイモの世界史/伊藤章冶/中公新書/2008
ジャガイモの歴史/アンドルー・F・スミス/原書房/2014
へんな毒 すごい毒/田中真知/ちくま文庫/2016
世界史を大きく動かした植物/稲垣栄洋/PHP/2018
海が運んだジャガイモの歴史/田口一夫/梓書房/2016
食中毒統計資料令和4~元年/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
食品中の天然毒素「ソラニン」や「チャコニン」に関する情報/農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/solanine/
有毒植物による食中毒に注意しましょう/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html