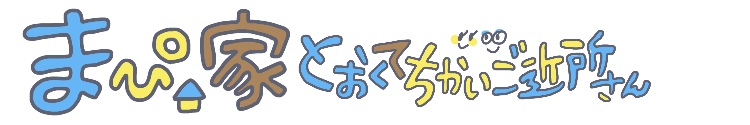6.食中毒対策
marcy
これらを踏まえて、
自分たちはどこに気をつければ
いいのかを、まとめておきます。
まずは、芽が出たり、
緑に変色しているじゃがいもを買わない。
また、保存場所は暗くて涼しい場所にする。
これは、日に当たると緑化が進むからでした。
あまり長期保存しない。
調理するときは皮を厚めに剥く、芽を取る。
未熟な小さいいもを皮ごと食べると
ソラニンの摂取量が増えるので、
量には気をつける。
また、ソラニンには苦味があるので、
食べてて苦いなと感じたら
食べるのをやめる。
僕はこの苦味に敏感で、
けっこう反応します。
pino
うんうん。
tomo
そうなんですか?
pino
ちょっと緑色の部分があるじゃがいもを
皮を厚めにむいて使ったとしても、
マーシーは「苦い」とか
「ピリッとする」って言って
食べられない。
marcy
そうそうそう。
pino
分かっちゃうから、
もう食べられない。
tomo
すごいじゃないですか(笑)
pino
わたしは食べられちゃうけど(笑)
marcy
僕はソラニンセンサー敏感なんで、
この記述は共感するんですよね。
pino
でもマーシーが言うから、
私もちょっとわかるようにもなってきて。
わかったうえで、判断するようにしてる。
tomo
(笑)
marcy
意識して食べると感じるよね。
tomoさんは、あんまり感じないですか?
tomo
いや…
そんなに感じたことないですねぇ…。
marcy
やっぱり、これは個人差がありますね。
pino
まぁ、知ってる知ってないの違いもあるかも。
このあと出合ったときに
わかるかもしれないね。
marcy
あぁたしかに。
tomo
じゃぁ、
いっかい芽をちょっと食べてみて…。
marcy
それは、やばい(笑)
pino
あぶないあぶない(笑)
tomo
ピリピリするなぁみたいな。
marcy
まだ、緑になった皮なら
いいかもしれないですけど、
芽は…(笑)
tomo
そうか、
芽がいちばん毒が多いですもんね(笑)
marcy
すぐ吐き出したらいいのか…?
カラダはるなぁ(笑)
ということで、
食べる人はこういったところに注意ですね。
tomo
ですね。
(食べるときの注意点)
・芽が出ていたり緑色になったところがあるジャガイモは、買わない
・暗くて涼しい場所に保管する
・長期間保存しないで、早めに食べる
・芽や緑色のところがあったら、皮を厚めにむいて取り除く
・未熟な小型のイモを多量に食べない(特に皮ごと食べるのは避ける)
・苦みを感じたら、食べないようにする(ソラニンは苦味がある)
[参考/内閣府 食品安全委員会e-マガジン]
marcy
また、栽培する側の注意点もあります。
日に当たると緑化が進むので、
土寄せをしっかりする。
熟して大きくなってから収穫する。
傷ができると、そこでソラニン増える。
だから収穫するときは、
傷をつけないように気をつける。
保管は暗くて涼しい場所にする。
「収穫した後、すぐ乾かすために
太陽に当てないように」という記載もありました。
tomo
そうか、湿るとカビの原因になるので
乾かしたくなりますものね。
marcy
すぐ出荷するといいですけどね。
pino
北海道の方は貯蔵するっていうよね。
marcy
うん、今後機会があったら、
こういうところに
注目しておいてもらえるといいかもです。
tomo
さつまいもとは違いますものね。
さつまいもは寒いところに置かないし、
むしろ温めるくらいで。
marcy
低温障害もあるし、
キュアリングもするし。
tomo
じゃがいもとは逆ですよね。
marcy
そうなんです、
じゃがいもは寒いところが好き。
これは、この後出てきます。
というわけで、
作る側・栽培する側にも注意点があるよ
という話でした。
tomo
はい。
(栽培するときの注意点)
・いも部分が地面から外に出ないよう、きちんと土寄せをする
・十分に熟して大きくなったジャガイモを収穫する
・収穫するときは、ジャガイモに傷を付けないようにする
・収穫しら暗くて涼しい場所に保管し、日光にあてないようにする (乾かすために長時間太陽に当てない)
[参考/内閣府 食品安全委員会e-マガジン]
marcy
そして、食中毒対策の最後に
もうひとつ。
ソラニン中毒の予防として、
γ線という放射線照射をして
発芽を防止するという対策が実施されている
というお話です。
tomo
なるほど。
marcy
これは知ってました?
tomo
いや、知らなかったですね。
marcy
ぴのちゃんは知ってるよね、
試験でたもんね。
pino
うんうん。
じゃがいもにだけ許される放射線。
marcy
そうそう。
では、この概要をみておきます。
じゃがいもの発芽防止のために、
コバルト60という放射線を
収穫後に照射します。
これをすると、
室温で8カ月くらいの発芽防止効果があると。
現在の日本で、食材に対して
放射線を照射できるのは、
じゃがいもだけです。
tomo
なるほど。
marcy
また、実際これを実施しているのは、
北海道にある1つの施設のみです。
pino
ふ~ん!
marcy
照射されたものは、
「照射済み」の表示義務があります。
だから全部のじゃがいもに
照射しているわけではなく、
一部そういうものもあるよ、
という認識です。
tomo
なるほど。
marcy
海外だと、他のいくつかの
作物にも許されています。
日本は今のところじゃがいもだけ。
なぜ放射線を当てるのかというと、
芽が出るからですよね。
芽は、細胞が分裂して出てくる。
そして細胞分裂が活発な部分は
放射線の感受性が高く、
照射するとそこに集中して吸収する。
するとDNAが壊れて、
細胞分裂、つまり発芽を防止できる。
pino
ふ~ん。
marcy
一点、放射線についての注意ですが、
「じゃがいもに放射線を当てている」のであって、
「じゃがいもを放射線物質で
汚染しているわけではない」ということ。
これを食べたからと言って、
体内で被曝するわけではないです。
あと、この施設のデータをみると、
「照射しても栄養素は変わらない」みたいですね。
pino
へぇ~。
marcy
これも、ソラニンを知らないと
そんな処理するなよっ!て思うけど、
毒のリスクを考えると
選択肢の1つなんだろなと、
納得につながるかな。
tomo
これは日本の場合ですよね。
marcy
そうです、海外だと、じゃがいもに加えて
他もやっているので、むしろ日本は厳しい方ですね。
以上、
ソラニン対策として、
こんなお話もあるよ、という紹介でした。
pino
国試で出るから、
もっとスタンダードにやってるのかと
思っていたけど、
実施しているのは一部なんだね。
北海道。
marcy
やっぱり「年中供給する」ってなったら、
必要になるのかも。
tomo
つまりγ線は、
食べた時の毒予防というより
保存のためにやっている感じが強いですね。
芽を出したくないために。
marcy
確かに!
芽が出たら、出荷できないですもんね。
pino
γ線やってるのって
いつからなんだろう。
marcy
ちょっと手元にデータはないけれど、
おそらく昭和からとかじゃないかな。
pino
最近。
地産地消している時代なら、
いらないか。
tomo
そうですよね。
*参考文献を基にしておりますが、厳密な考証は行っておりません。あくまで「趣味のおしゃべり」として、楽しんでいただけると幸いです。
参考文献
ジャガイモのきた道/山本紀夫/岩波新書/2008
ジャガイモの世界史/伊藤章冶/中公新書/2008
ジャガイモの歴史/アンドルー・F・スミス/原書房/2014
へんな毒 すごい毒/田中真知/ちくま文庫/2016
世界史を大きく動かした植物/稲垣栄洋/PHP/2018
海が運んだジャガイモの歴史/田口一夫/梓書房/2016
食中毒統計資料令和4~元年/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
食品中の天然毒素「ソラニン」や「チャコニン」に関する情報/農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/solanine/
有毒植物による食中毒に注意しましょう/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html