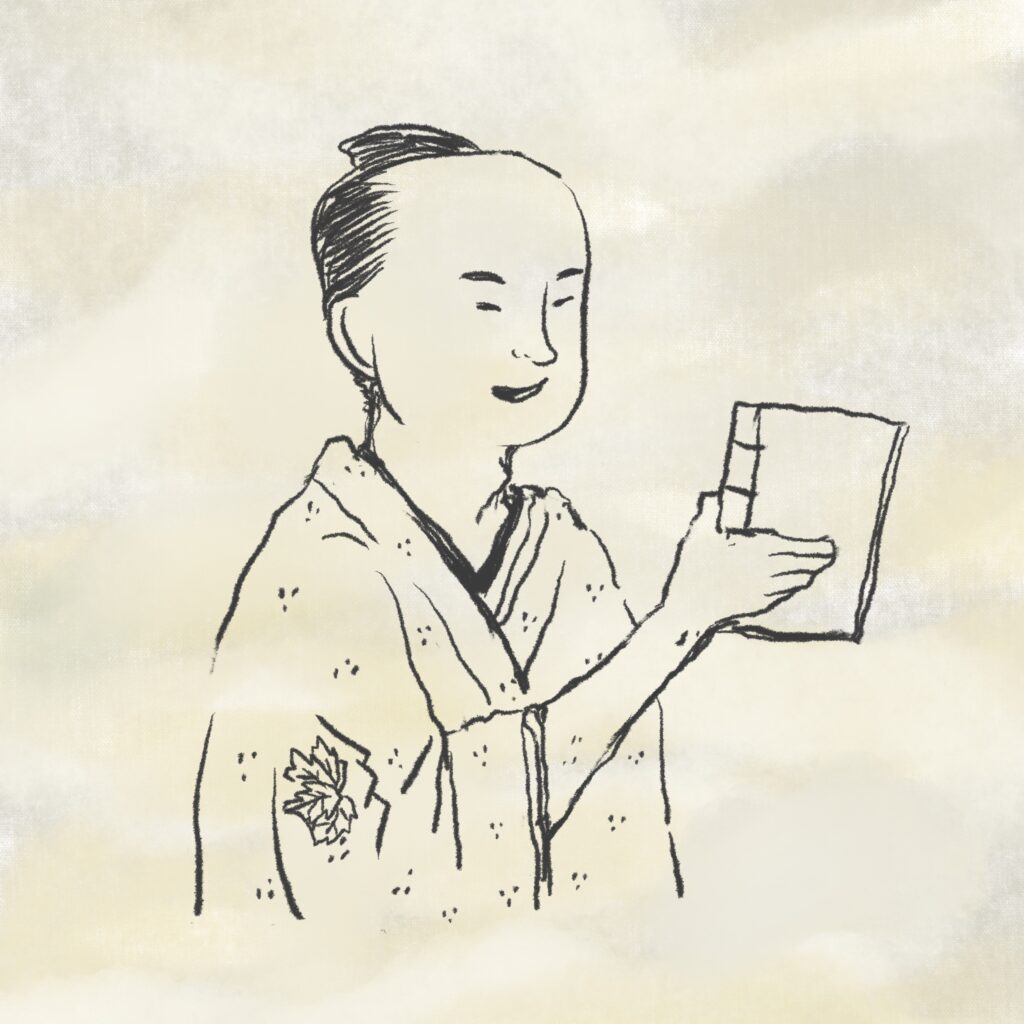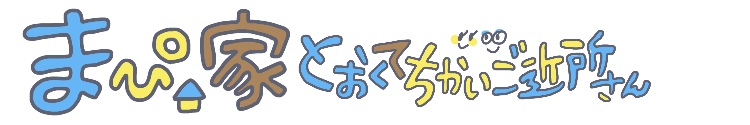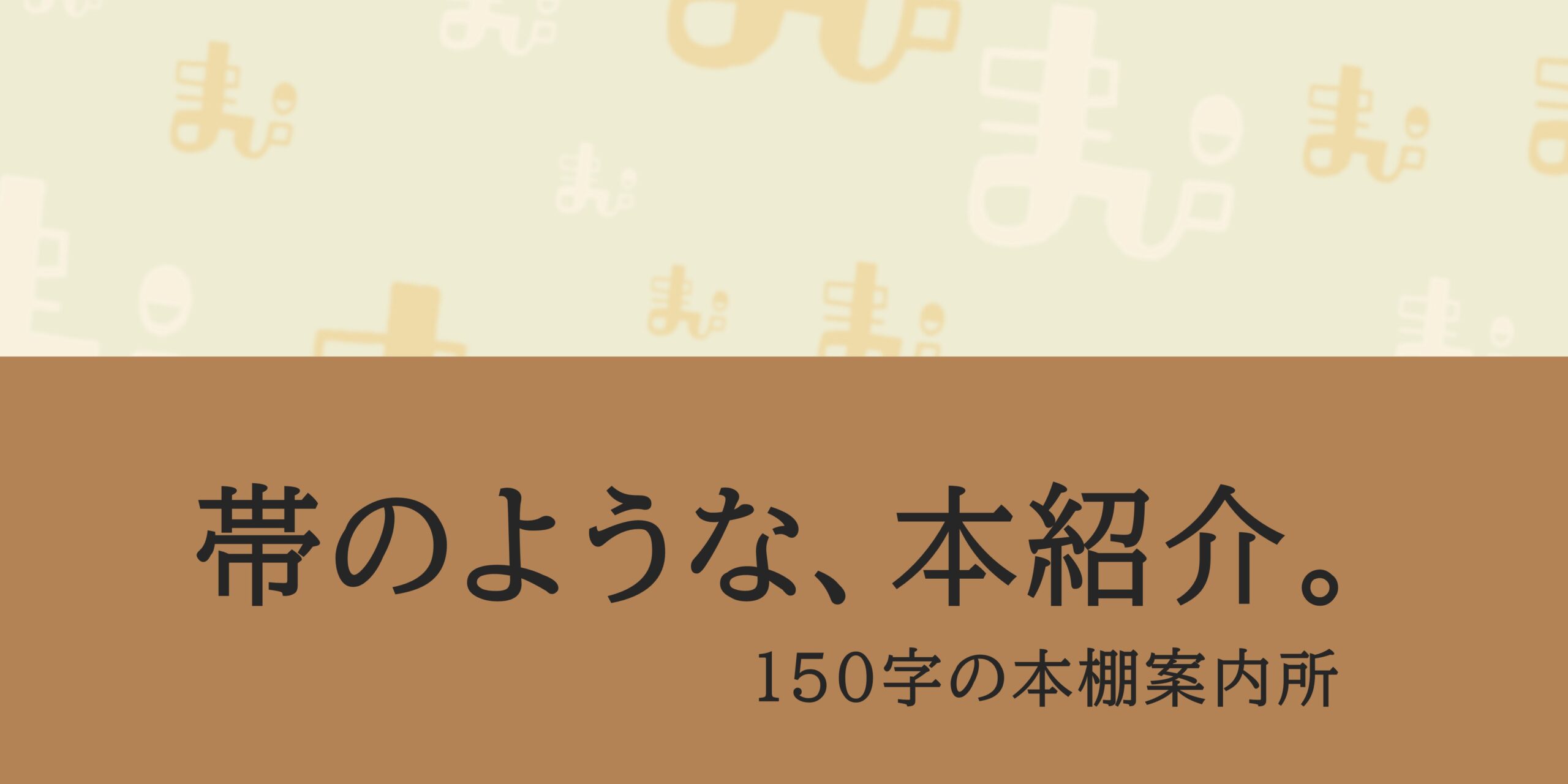
【ご案内】
本の帯のように、自分の言葉で、短めに、本を紹介する場所です。だいたい150字以内でお願いします。1行でも大丈夫です。ひとつの本をひとりで何度か紹介していただいても構いません。静かな場所なので、書影の閲覧や本へのリンクはセルフサービスとなっております。気になったものがあれば、ぜひ検索してみてください。
棚番号
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14
new『味ことばの世界』
瀬戸賢一・他 / 海鳴社(2005)
「おいしさの表現」に関するレポート集、第二弾。一緒に食べれば「おいしいね」ですべて伝わるのに、一歩その場を離れれば、どうやっておいしさを伝えるのかに苦心する僕たち。それはなぜか、ではどうするかなど、様々な角度からの考えが載っている。ある意味で、「おいしさ」と「それを言い表したい人間」との闘いの記録。(まーしー)

『さみしい夜にはペンを持て』
古賀史健 / ポプラ社(2023)
頭の中にある「ことばにならない思い」を、「コトバミマンの泡」と表現したのは発明だと思う。実は言葉よりも多いその泡と、どんなふうに接していけばいいのか。それは、誰にも習ったことのない自分とのコミュニケーション術でもあり、自己治癒的な行為でもある。いや、でも、そんなことを気負わず楽しく読める本。(まーしー)

『ざらざらをさわる』
三好愛 / 晶文社(2020)
三好さんの素直さを、見習いたい。いいとか悪いとかではなく、そういう経験をしたこと、感じたことが、等身大で書いてある。「ざらざら」と表してくれたことで、自分の「ざらざら」も、考えるきっかけをくれた一冊。(ぴの)
すごい。文章も絵も、その人自身もおもしろいし、それらがぜんぶかけ合わさって、ひとつにまとまっている。ほんとうに、本人にしか書けないなぁと思う、イラスト&エッセイ集。読むとたしかに、ざらざらしている。(まーしー)

『酒をやめられない文学研究者とタバコをやめられない精神科医が本気で語り明かした依存症の話』
松本俊彦・横道誠 / 太田出版(2024)
全体を通して、依存症に関する主観的なことと、客観的なこと、感情的なことと、論理・科学的なことが、ちょうどいいバランスで語られているのは、当事者だからできることだと思う。とてもリアルで、身近に感じる語り。弱さの開示は、強さだと思う。(まーしー)

『動物たちは何をしゃべっているのか?』
山極 寿一・鈴木 俊貴 / 集英社(2023)
鈴木さんと山極さんが、動物の世界に飛び込んできた話を聞くと、私たちが「動物の世界を知る」ことって、「人間の世界から眺めてる」だけだったなぁと気づいた。動物たちの世界に、もう一歩踏み込んで想像してみることの面白さを教えてくれた一冊。(ぴの)
ゴリラの研究者と、シジュウカラの研究者による対談。「人間とその他の動物」ではなく、「人間と比べて動物の知能はどれくらいか」でもなく、人間もそれぞれの動物も同じ視座で理解しようとする姿勢は、いま言われている「多様性」の次のステージだと感じる。スラスラ読めるのに、どんどんハイライトがやってくる。(まーしー)
タイトルの「動物たち」って、ゴリラや鳥のことだと思いました? もちろん、その話から始まるのだけれど、話はだんだんと、進化のグラデーションのように、「人間」へと変化していく。むしろ最後は、人間とはどんな動物か?が見えてくる。注釈や写真による解説も丁寧でうれしい。(まーしー)
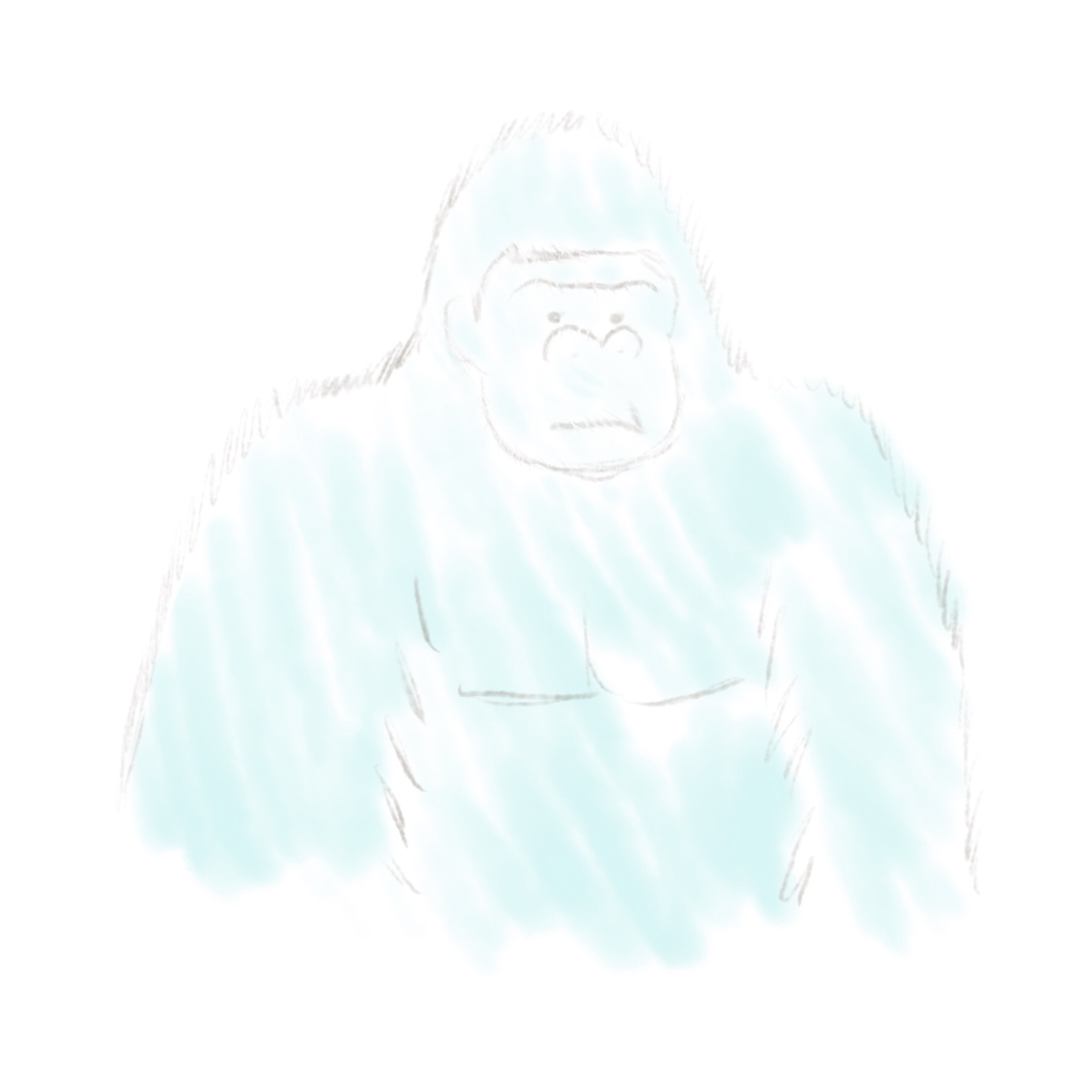
『転職ばっかりうまくなる』
ひらいめぐみ / 百万年書房(2023)
よく、和食は引き算だと言われる。食べられない部分やアクを抜き、できるだけ何もせずに、素材そのものを活かす。「おいしい」は、作るものではなく、引き出すもの。本書は、まさにそんな和食みたいなエッセイだった。飾らず誇張せず書かれた正直な文章が、その人本来の「おもしろさ」を表す。その純度に感化される。(まーしー)

『憶えている 40代でがんになったひとり出版社の1908日』
岡田林太郎 / コトニ社(2023)
誰かの日常が書かれた文章には、明確に主張や信念、夢、挫折などが記されているわけではない。けれど一方で、その全てが含まれているようにも思う。その人の人生の一部を、ちょっとなぞる。そこで共有されたものは、いつのまにか自分の糧になる。(まーしー)

『cook』
坂口恭平 / 晶文社(2018)
料理というものの価値を、味や栄養ではなく、「料理する」という行為自体に見出す視点に驚く。またそれは、料理本に対しても同様で、「レシピ」ではなく、その人の「料理の痕跡」に残るおもしろさをはじめて知った。あらためて、料理が楽しくなった。(まーしー)

『「分かりやすい説明」の技術』
藤沢晃治 / 講談社(2002)
いろいろ読んだ中で、自分にとって最も分かりやすかった一冊。分かるとはなにか、説明とはなにかが、簡潔に書かれている。さらに[おわりに]では、「分かりやすいことは必ずしも正しいか」という提起がされ、盲点にまで納得する。(まーしー)
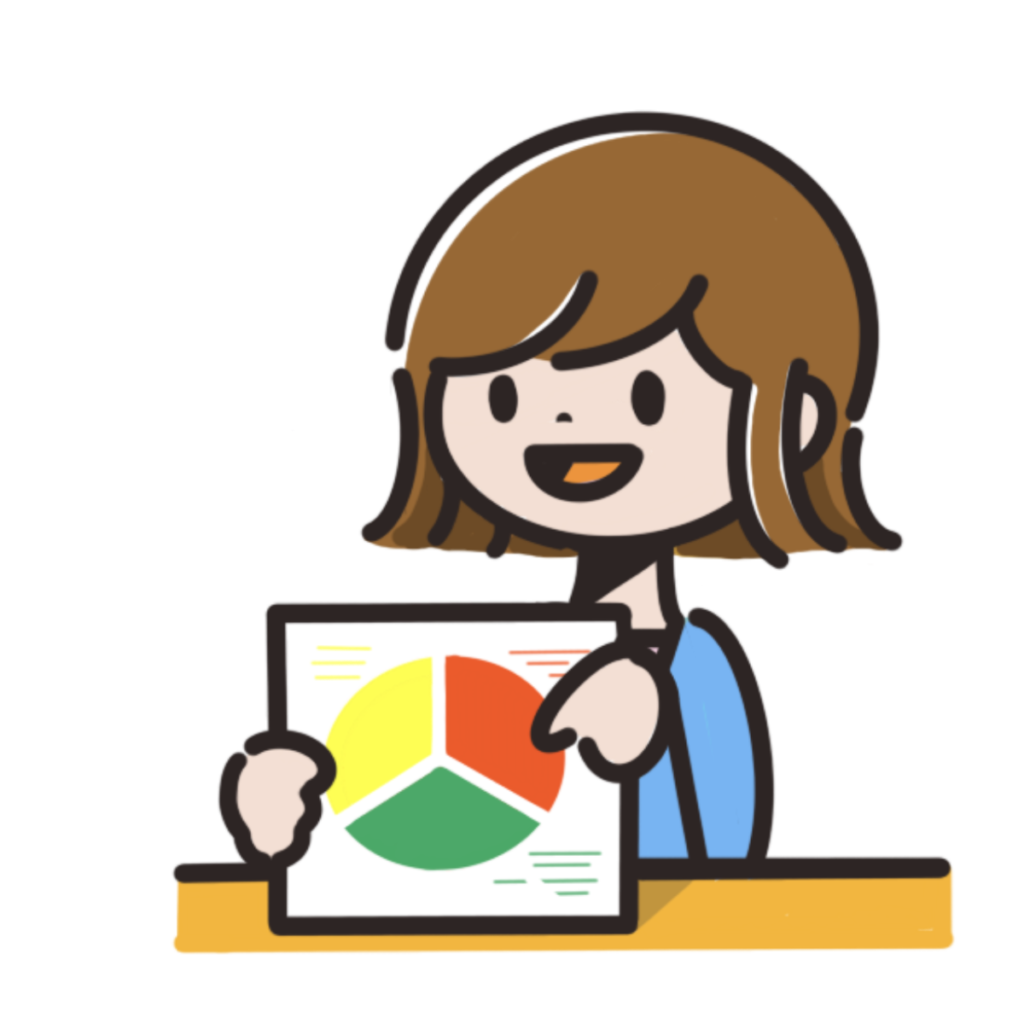
『八百屋の野菜採集記~「見る・知る・食べる」で楽しむ旬野菜とレシピ』
尾辻あやの / 大和書房(2023)
野菜の図鑑であり、レシピ本であり、エッセイでもあるが、そのどれにも当てはまらない著者の視点がある。単なる材料ではなく、個性を持ったひとりとして野菜と向き合い、そして出会っていく態度は、自分にとっての理想だった。(まーしー)

『夜と霧 新版』
ヴィクトール・E・フランクル /みすず書房 (2002)
強制収容所を体験した心理学者が語る、人間の本質。収容所の悲惨さではなく、苦難に直面した人間の立ち振る舞いと、そこから見えてくる人間そのものに焦点が当てられる。人生の意味をこんなふうに解釈する本は、他にない。自分の中の、ホモ・パティエンス(苦悩する人)部分が肯定される。(まーしー)

『古くてあたらしい仕事』
島田潤一郎 / 新潮文庫(2024)
ひとり出版社の「夏葉社」。いい本を丁寧につくり、丁寧に届けるこの会社が、どのように生まれ歩んできたのかを語るエッセイ。だけども、ものづくりの本質や、人としての振る舞い方、弱さの価値のようなものがにじみ出ており、付箋を貼る手が止まらないバイブルだった。(まーしー)
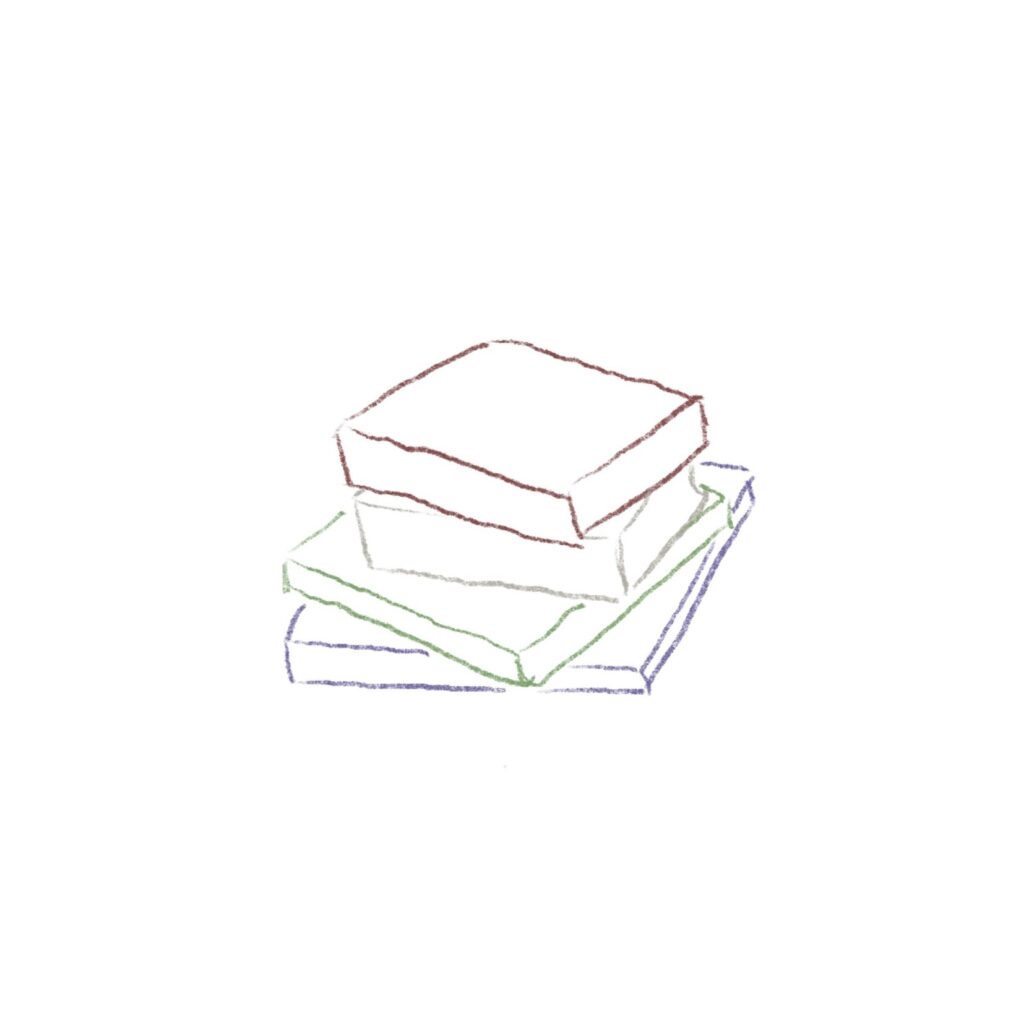
『生きのびるための事務』
坂口恭平 / マガジンハウス(2024)
もし、「学校で習わないこと」という学校の授業があるなら、まちがいなく教科書になる本だと思う。自分の好きなこと、やりたいことを計画的に進めることは、「成功」ではなく「生きること」につながっている。そんなこと、今まで誰も言ってくれなかった。(まーしー)
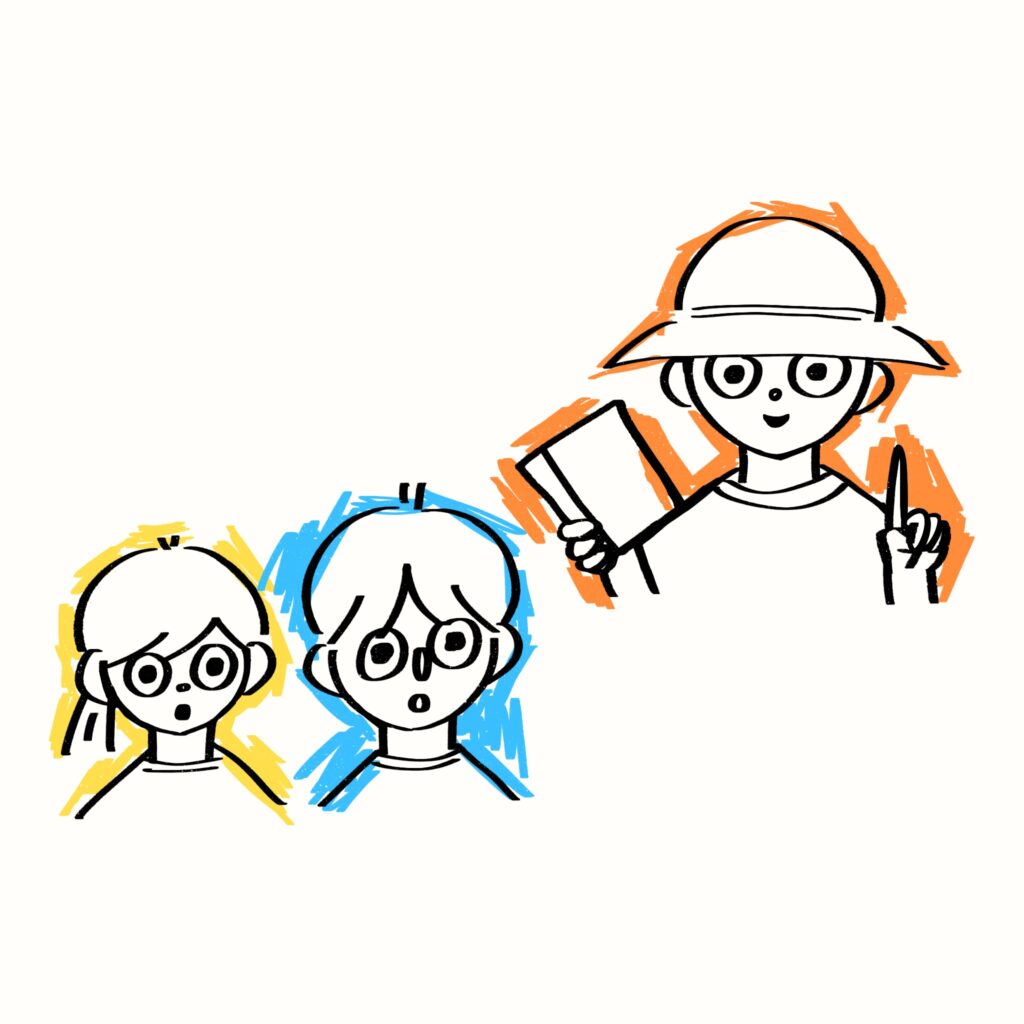
『蔦屋』
谷津矢車 / 学研プラス(2014)
だれかと何かをつくることは、楽しい。それを届ける場をつくることも、それで何かを動かそうとすることも、その大変さも、虚しさも含めて楽しい。しかもそれは、巻き込んだ方も、巻き込まれた方も。この本を読んでいると、きっとそうなんだろうと思う。江戸時代の版元、蔦屋重三郎の人生を描いた小説。(まーしー)
もし、人の縁が糸のようにつながっていたら、たった一人でも、たくさんの人を、世の中を、動かすのは簡単かもしれない。かるく引っ張ればいい。でも実際にそんな糸はなく、僕たちが「つながり」と呼んでいるものの正体は、弱い磁力のようなものだ。けれど、それを糸のようにつないで、新しいものを創っちゃう人がいる。(まーしー)