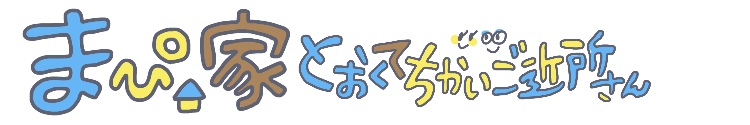第6話 振り返りトーク

メンバー


1.野菜は変化してきた
marcy
今回調べてみての感想なんですけど、
毒があるのは知っていましたけど
野生種から比べたらかなり
低減されているじゃん!という
視点の発見がいちばんおもしろかったです。
あと、僕たちがイメージする野菜って
そっかすべて栽培種の話かって思いました。
tomo
そうですよね。
marcy
その栽培種がはじめから
存在していたように感じてますけど、
そうじゃないんだなぁって。
あと、僕たちが野菜を育てるときは
種や苗を植えて収穫するまでですけど、
人類史視点で考えると
野生種から栽培種に変化させていくことも
すべて「野菜を育てる」なのかもと(笑)
tomo
その通りだと思います(笑)
これまでが積み重なって
食べやすく美味しいものができたのは、
忘れちゃいけないことだなと
すごい感じています。
marcy
そうですよね~。
tomo
そこを勘違いして
自然に進化してきたものとして
扱いすぎると、それもちょっと
ズレてしまうというか。
marcy
なるほど、なるほど。
ジャガイモからしたら、
日本という環境も
いちばん心地いい場所ではないし。
tomo
そうですよね。
植物なんだけど、他の草とは違って
ヒトが選んできたものなので。
毒の話も、ヒトが食べやすい種を
残してきているので、おサルさんにも
あっさり食べられちゃうというか。
動物も食べやすいのを狙っているし。
pino
うんうんうん。
marcy
原種だったら、
きっと食べられないでしょうね。
tomo
だから、野菜作りというのが
自然そのものではなく、
人間の都合がだいぶ
入っているなっていうのは、
忘れちゃダメだなって思いますね。
marcy
いやぁ、おもしろいです。
実際に育てている人の意見は違うなぁ。
今の野菜を自然に栽培しすぎると、
ある意味で不自然な部分があると。
tomo
ある意味そうですね。
また、そうやって育ってきた種を
今度は逆に野生のきびしい条件で育てると
本来持っている野性味を発揮して
どんな味になるのか。
あるいは、カラダにいいみたいなことが
起こる可能性とか。
そういう、昔に戻るのではなく
次の野菜の可能性を持っているのかな
という思いもあります。
marcy
あぁたしかに、たしかに。
tomo
慣行栽培が前提の品種だけではなくて、
農薬がなくても育つ在来種や固定種も
残っていけばいいなと。
marcy
なるほど。
tomo
昔に戻るのではなくて、
新しい進化を生み出す要素になれば
おもしろいなと思います。
marcy
品種の種類のバリエーション
だけじゃなくて、
肥料や農薬の必要性による多様性は、
必要かもしれないですね。
tomo
あぁ~そうですね。
だから、今いろいろな名前が
ついているジャガイモが
もとは同じ種類だったみたなことが、
さらに今後も起こっていくよねって
すごい思います。
marcy
いいですねー、おもしろい。
*参考文献を基にしておりますが、厳密な考証は行っておりません。あくまで「趣味のおしゃべり」として、楽しんでいただけると幸いです。
参考文献
ジャガイモのきた道/山本紀夫/岩波新書/2008
ジャガイモの世界史/伊藤章冶/中公新書/2008
ジャガイモの歴史/アンドルー・F・スミス/原書房/2014
へんな毒 すごい毒/田中真知/ちくま文庫/2016
世界史を大きく動かした植物/稲垣栄洋/PHP/2018
海が運んだジャガイモの歴史/田口一夫/梓書房/2016
食中毒統計資料令和4~元年/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
食品中の天然毒素「ソラニン」や「チャコニン」に関する情報/農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/solanine/
有毒植物による食中毒に注意しましょう/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html